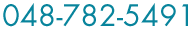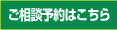民事事件と刑事事件
弁護士が裁判所で扱う事件は大きく分けて民事事件と刑事事件に分かれます。
交通事故を例にご説明します。
- 〔民事事件〕
- 交通事故でケガを負ったり自動車を壊された被害者が加害者に対して損害賠償を求めるのが民事事件です。
損害賠償とは、治療費や慰謝料、自動車の修理代などの金銭を支払うよう加害者に求めていくものです。
弁護士は加害者側と交渉したり(多くの場合は加害者が加入する任意保険会社と交渉することになります)、 加害者に対して民事上の訴えを提起して損害賠償を求めていきます。
- 〔刑事事件〕
- まず警察官や検察官が捜査を行います。
捜査とは、現場の実況見分を行ったり、加害者を被疑者として取調べたりして証拠を集めることをいいます。
その後、事案に応じて検察官が加害者を起訴して、裁判所に対して罰金や懲役刑等の処罰を求めていきます。
交通事故の場合は、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)などが適用されます。
これが刑事事件です。
刑事事件には、自動車運転過失致死傷罪の他、窃盗罪(刑法235条)、業務上横領罪(刑法253条)、傷害罪(刑法204条)などがあります。
以下では、刑事事件の流れについてご説明いたします。
公訴提起前
捜査
- (1)捜査機関
- 捜査を担当するのは、警察官と検察官です。
捜査機関は犯罪が行われたと考える場合に捜査を開始し、被疑者を特定したり証拠を集めたりします。
通常は、まず警察官が中心となって捜査を行い、書類や証拠物とともに事件を検察官に送致(送検)することになっています。 - ※なお新聞などでは「容疑者」という用語が使われていますが、法律上の用語としては「被疑者」が使われます(刑事訴訟法30条,199条など)。
- (2)捜査の内容
- 具体的な捜査の内容としては、犯行現場の実況見分、被疑者の自宅などの関係場所の捜索、被疑者・参考人の取調べ(事情聴取)などがあります。
捜査機関は、必要に応じて被疑者や関係場所に強制的に立ち入って捜索を行ったり、被疑者を逮捕したりすることができます。
これらの捜査は、(1)で述べたとおり通常は警察官が中心となって行います。 - 検察官は警察官から送られてきた書類や証拠物を見て、足りない点があれば警察官に補充捜査を命じます。
また、検察官は必要に応じて自ら補充捜査を行います。
多くの事件では、検察官は自ら被疑者・参考人の取調べをして、供述調書(検察官面前調書)を作成します。
- (3)任意捜査と強制捜査
- 捜査は、任意捜査と強制捜査に分かれます。
任意捜査は、強制力によらない捜査つまり人の身体や財産などの権利を侵害しないで行う捜査をいいます。
交通事故が発生した公道上で実況見分を行うことは、誰の権利も侵害しないので任意捜査になります。 - また捜査される側の同意を得てする捜査も任意捜査に含まれます。
よくニュースなどで「任意同行を求めて事情聴取を行った」と報道されることがありますが、被疑者・参考人の同意の上で警察署に同行してもらい、取調べを行うことはここでいう任意捜査にあたります。 - これに対して強制捜査とは、人の身体や財産などに対する強制を伴う捜査をいいます。
警察官が被疑者の身体を拘束したり(これを逮捕といいます)、家の人の同意なく家に立ち入ったり、所有物を差し押さえたりすることが強制捜査の一例です。
これらの強制捜査(強制処分ともいいます)をするためには、原則として裁判官の発付する逮捕状、勾留状、捜査差押許可状などの令状が必要になります。
これは不当な人権侵害を防止するため、こうした強制処分は裁判官の発付する令状により行うべきことを憲法が要求していることに基づくものです。
検察官による起訴・不起訴の決定
- (1)起訴・不起訴の判断
- 検察官は捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。
起訴するか起訴しないかの判断をする権限は、検察官だけが持っています。 - 被疑者が罪を犯したという疑いがない、つまり被疑者が犯人ではないと判断する場合や、
被疑者が犯人であると証明する十分な証拠がないと判断する場合には、検察官は事件を起訴しません。
これを「嫌疑なし不起訴」・「嫌疑不十分不起訴」といいます。 - これに対して、被疑者が犯人であると証明できる十分な証拠が揃っていると検察官が判断する場合であっても、
犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重および情状、犯罪後の情況といった様々な事情に照らして、あえて起訴をして処罰を求める必要はないと考えるときには起訴しないことができます(刑事訴訟法247条・起訴便宜主義)。
これを特に「起訴猶予」といいます。 - この検察官の不起訴の判断には、裁判所など第三者の事前チェックは入りません。
つまり検察官は、ある事件を起訴するか不起訴にするかについて、強大な権限を有しているのです。
- (2) 検察官による起訴(公訴提起)
- 検察官が起訴することを相当と考えて裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると、刑事事件の裁判手続が開始されます。
「被疑者」は起訴されると「被告人」と呼ばれるようになります。 - 起訴状には検察官が主張する「罪となるべき事実」などが書かれています。
公判で主に審理するのは、起訴状に書かれている事実です。 - 審理する裁判所は、原則として、 罰金以下の刑は簡易裁判所、 それ以外の罪の事件については地方裁判所 となります。
第一審裁判の手続き
概要
第一審の公判手続は、以下のように進んでいきます。
- ・争点及び証拠の整理手続(行わない場合もあります)
- ・冒頭手続
- ・証拠調べ手続
- ・弁論手続
- ・判決宣告手続
争点及び証拠の整理手続
公判の審理を計画的かつ迅速に行うために行う手続きです。
事実に争いがある事件や重大事件で活用します。
子の手続きは公判前整理手続と呼ばれます。
まず、弁護人と検察官の双方の主張の中で、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込みます。
その上で、争点を立証するためにはどのような証拠が必要か、それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当か、などを協議します。
そして、公判の日程をどうするか、証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか、証人はいつ尋問するかなど、判決までのスケジュールを立てます。
公判の途中でも必要がある場合は、公判期日の合間に、公判前整理手続の場合と同様に争点や証拠を整理していく手続きもあります。
これを期日間整理手続きといいます。
冒頭手続
冒頭手続では、主に以下のような手続きを行います。
人定質問:裁判長が被告人に氏名、職業、本籍などを聞き、被告人が検察官により公訴を提起された者に間違いないかどうかを確かめます
起訴状朗読:検察官が起訴状を朗読し、審判の対象を明らかにします
権利告知:裁判長が被告人に黙秘権その他の権利を説明します
陳述の機会の付与:起訴状に書かれた公訴事実について、被告人および弁護人が意見を述べます
なお冒頭手続の段階で、裁判官は起訴状しか見ていません。
裁判官の手元には起訴状しかないのです。
これを起訴状一本主義といいます(刑事訴訟法256条6項)。
審理が始まる前に、検察官が集めた証拠つまり被告人に不利な証拠ばかりを裁判官が見て予断・偏見を持ってしまうことを防止するためです。
証拠調べ手続
- (1) 検察官の立証
- 最初に検察官側が立証します。
刑事事件においては、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれています。
そこでまず検察官が証拠によって公訴事実を「合理的な疑いを入れない」程度にまで証明するための立証活動をしなければならないわけです。 - 検察官はまず冒頭陳述を行います。
証拠調べの冒頭で行う陳述ですから、冒頭陳述と呼ばれます。
冒頭陳述では、検察官が証拠によって証明しようとする事実=検察側のストーリーを明らかにします。
その上で検察官は証拠の取調べの請求を行います。
それに対して弁護側は、採用すべきでない証拠があれば裁判所に意見を述べます。
裁判所は弁護側の意見を聞いた上で、法律に基づいて証拠を採用するかどうかを決定します。 - 証拠調べでは、たとえば事件現場の実況見分調書の取調べを行ったり、検察側証人の証人尋問を行ったりします。
- (2)弁護側の立証
- 弁護側の立証は、検察官の立証が「合理的な疑いを入れない」程度にまでは証明されていない、と裁判所に考えさせるだけで十分とされています。
無罪を争う事件では、弁護人はそのための立証に力を注ぎます。 - 有罪であること自体に争いがない事件では、被告人にとって有利な情状を証明することが主な目的になります。
- (3) 弁護人の役割
- 刑事訴訟法では、被告人側・検察側がそれぞれ証拠の収集や公判への提出等を行うことになっています。
検察官は法律の専門家ですし、警察に対して捜査を命じて証拠を集めることも出来ます。
しかし被告人は一個人ですから、そうはいきません。
被告人と検察官の力の差は歴然です。
そこで、弁護人が被告人の代理人・補助者として、検察官の立証に対して反証したり、不利な証拠が採用されることを阻止したり、被告人に有利な事情を独自に立証したりしていくことが非常に重要なのです。
弁論手続
まず検察官が、証拠調べの結果を踏まえて事件のポイントについて意見を述べます。
これを論告といいます。
通常は、その最後に求刑を行います。
次に弁護人からも事件のポイントについて意見を述べます。
最後に被告人自身が意見を述べます。これを被告人の最終陳述といいます。
判決宣告手続
裁判所が判決の言渡しをします。
控訴及び上告
被告人側も検察官側も第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴することができます。
高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます。
簡易裁判所の刑事事件について
簡易裁判所で審理される刑事事件は、罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な罪です。
簡易裁判所は、通常、禁錮以上の刑を科することはできません。
簡易裁判所が扱う刑事事件の代表例は、略式手続です。
これは、法廷を開かない書面審理で行われます。
裁判官は検察官が提出した証拠を検討して、相当と認めた場合に、略式命令を出すことになります。
略式手続で行う場合は、被疑者の異議がないことが必要です。
略式命令で科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金又は科料に限られます。
略式命令に不服があれば、正式裁判の申立てをすることができます。
その場合には、略式命令は効力を失います。